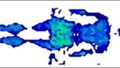今やウレタンを使ってないマットレスはないと言っても過言ではありません。

ネットで良いマットレスを調べてたり、寝具店で色々なマットレスを見ても、
高反発マットレス、低反発マットレス、ポケットコイルマットレス、ボンネルコイルマットレス、快眠マットレス、腰痛対策マットレス、、、など色々とありすぎてわからない!
なんてことありませんか?
マットレスの弾力性、反発力の視点で見れば低反発マットレス、高反発マットレスで分かれるし
素材で見ればコイルスプリング、ウレタン、パームマットレス、ラテックスマットレスなど。
でも、どんな種類のマットレスでもほぼウレタンが使われてます。
スプリングだけのマットレスなんて見たことがないし、
機能性を重視する敷布団でもウレタンが使われてるし、エアウィーブやブレスエアーやエアファイバーのマットレスでも一部ウレタンは使われてます。
その理由はシンプルでウレタンの寝心地を調整しやすいから。
今回はウレタンマットレスにはどんな種類があるのか、どんなメリットやデメリットがあるのかをスッキリと解説します。
目次
ウレタンマットレスのメリットとデメリット
ウレタンマットレスを大きく分けると高反発ウレタン、低反発ウレタンとありますが、まずはウレタンそのもののメリットとデメリットについて。
体圧分散に優れてる
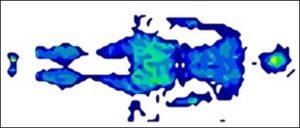
色々な寝具メーカーがマットレスにウレタンを使う理由は、低コストで耐久性が高く良い寝心地を実現できる素材だから。
ウレタンマットレスの寝心地に近い素材としては天然ラテックスマットレスがありますが、これは天然のゴムの木からゴム樹液を集めて加工してとかなりの手間がかかって価格も高くなりがち。
それよりも、硬さや弾力性をコントロールしやすくて低価格で製造できるウレタンの方がメーカーも私たち利用者にもメリットがあるんです。
NASAのスペースシャトルや宇宙服でも衝撃吸収材としてウレタンが使われたこともあって、
一時はバカの一つ覚えのように色々なウレタンマットレスでは「NASAの技術をから生まれた」と繰り返されてました。
それだけ衝撃吸収率、つまり体圧分散が高く、加工しやすい素材で今やマットレスだけじゃなく枕でもウレタンはかなり使われてます。
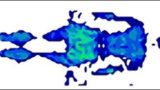
マットレスの硬さを調整しやすい
ウレタンはポケットコイルなどのコイルスプリング系マットレスの詰めもの使われています。
より柔らかな寝心地、または腰が沈まないような硬い寝心地。
スプリングだと調整が難しいマットレスの硬さ、弾力性をウレタンは加工しやすく、体圧分散や良い寝姿勢などマットレスの機能性を求めるにとにとってはかなり調整しやすい素材です。
ウレタンマットレスはダニがつきにくい!
ウレタンは人のフケや垢、ほこりなどが付着しにくい性質があるのと、ダニが奥まで入り込むことが出来ないのでウレタンマットレスそのものがすでに防ダニされた素材というのは、寝具のダニが気になる人にとってはかなり魅力的。
羊毛、羽毛、い草・畳マットレスだったりパームマットレスなどダニが付きやすい素材では、防ダニ加工されてるものが多いですが、防ダニ加工の効果は時間がたつとともに弱まってきます。
もちろん、ウレタンマットレスを使っていてもマットレスカバーや敷きパッド、掛け布団などのダニ対策は必要ですがマットレスに比べれば大したことありません。

クリーニングは比較的面倒
一方、デメリットとしては一般的な和布団と比べるとクリーニングがちょっと面倒という点も。
もし羊毛などの繊維系の素材であれば洗濯機で洗えるものもあるし、エアウィーヴのような素材も水洗い出来ます。

ただウレタンマットレスの場合、これは枕でも同じですが水洗いすると間違いなく変形します。
寝具として使い物にならないくらい。
通気性の高いウレタンマットレスの場合寝汗は下に落ちるので、底面の除湿だけ気を付けてれば大丈夫。
また除機掛けなどは簡単に出来ますが、おねしょ、何かをこぼすなどした場合のクリーニングはちょっと大変です。
ウレタンマットレスの汚れ対策としては、敷きパッドを使うこと。
特に防水性能が高いかどうかを気にしなくても、普通の敷きパッドで十分ですがウレタンマットレスの汚れ防止としてシーツだけじゃなく敷きパッドは一緒に使うことがおすすめです。

布団乾燥機を使う場合は少し注意
ウレタンマットレスは高温にも注意が必要!
ウレタンマットレスも枕も、日干しするのはNG。
今まで使ったことがある人だったらわかると思いますが、日干ししても大丈夫なウレタンマットレスや枕は見たことがありません。
布団を使っていた人は定期的に干しする習慣があると思いますが、ウレタンマットレスは陰干しが基本です。
また、布団乾燥機も50℃以上の高温モード、ダニ退治モードでつかうとマットレスが劣化することがあるのでNG。
もともとウレタンマットレスにはダニは寄せ付けない特性があるので、ダニ対策として布団乾燥機を使う必要はありませんが、冬にちょっと暖かくつかいたいとか、マットレスの湿気を飛ばしたい場合は低温モードで使うことをおすすめします。
高反発ウレタンと低反発ウレタンの違い
ウレタンマットレスを大きく分けると高反発ウレタンマットレスか低反発ウレタンマットレス。
中には中反発、優反発などもありますが99%以上は高反発か低反発に分かれます。
低反発ウレタンマットレスの魅力とリスク
テンピュールやトゥルースリーパーで有名な低反発マットレス。
マットレスに反発力がないので体のどこか特定部分に圧迫感を感じることがない柔らかで包み込まれるような寝心地が魅力。
ただ沈み込みすぎると、寝返りが打ちにくい、腰に負担がかかった寝姿勢を長時間摂るというのがリスク。
寝返りが打ちにくくなるので、マットレスも蒸れやすくなるし腰痛の原因にもなります。
とはいっても体圧分散に優れた低反発マットレスはなかなか魅力的なのは間違いありません。
低反発マットレスのリスクを回避して使う場合は、厚さ5cm程度のマットレスを選んで硬い布団またはマットレスの上に上敷きとして使うのがおすすめです。
分厚い低反発マットレスの場合は腰にかなり負担がかかるはずなので。
高反発ウレタンマットレスの魅力とリスク
マニフレックスや腰痛対策マットレスのモットンで有名な高反発マットレス。
ウレタンの反発力がたかいので、体が沈み込みすぎず、寝返りが打ちやすい、腰に負担がかからない寝姿勢が魅力。
ただ、高反発といっても上限がないので反発力が高すぎるマットレスは肩や腰に圧迫を感じることもあるのがリスク。
高反発マットレスのリスクを回避して使う場合は、自分の体格とマットレスの硬さの適性をチェックすること。
寝具店で試し寝するときは、担当者にアドバイスをもらうことがおすすめです。
高反発マットレスのモットンは腰痛持ちの口コミが良いですが、その理由は体格に合わせてマットレスの硬さを選ぶ基準があるからです。
以外と高反発マットレスには使う人の体型と硬さ選びの基準がないものが多いので今後改善してほしいところです。